 |

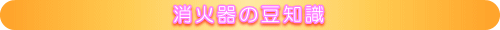
 |
 |
 |
 |
 |
火災は主に以下の3種類に分けられます。
- 普通火災(A火災)
木材、紙、繊維などが燃える火災
- 油火災(B火災)
石油類、その他可燃性液体や半固体の油脂類などが燃える火災
- 電気火災(C火災)
電気設備のショートによる火災
消火器もこれらに合わせ、白・黄・青のマークで適応する火災の種類を表しています。
|
 |
 |
 |
 |
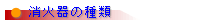 |
 |
 |
 |
 |
消火器は主に以下の様な種類があります。
- 粉末消火器
瞬時に炎を抑え消火できますが、浸透性がないため物により再び発火する恐れがあるので注意が必要です。
- 強化液消火器
薬剤が水溶なので浸透性があり木材等に有効です。また、冷却効果もあります。 但し、水との作用で発熱する危険物には使用できません。
- ガス系消火器
粉末や水溶性の薬剤を放出しないので、油火災や電気火災に特化しており消火による被害を最小に抑える事ができます。
但し、その殆どが普通火災には効果がありません。
- 住宅用消火器
住宅火災を対象に小型・軽量化され持運びに便利です。
消火剤のタイプも『粉末』『強化液』と、それぞれ用意されてます。
また、自動消火機能付きのものもあります。
 |
※ 向かって左から…
・粉末消火器 ・強化液消火器 ・ガス系消火器 ・自動車用粉末消火器
・住宅用強化液消火器 ・住宅用粉末消火器 ・住宅用自動消火機能付き消火器
|
|
 |
 |
 |
 |
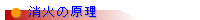 |
 |
 |
 |
 |
燃焼が起こり持続する為には、燃えるもの ・ 空気(酸素) ・ 高温
の3つが不可欠であり、これを燃焼の三要素と言います。
従って火を消すには、
- 除 去
燃焼物を取り去る
- 窒 息
酸素を遮断または酸素濃度を薄くする(通常、大気中の酸素濃度は21%ほどであるが、これが15%になると火は消えます)
- 冷 却
冷やして温度を下げる
- 抑 制(負触媒)
燃焼物の炭素と空気中の酸素と熱の連鎖反応を抑制または遮断する
これらのいずれかを行えばよく、この四つを消火の四要素と言います。
そして、消火器はこの中の 窒息・冷却・抑制作用のいずれかを活かし火を消します。
|
 |
 |
 |
 |
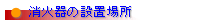 |
 |
 |
 |
 |
初期消火により火災を最小限にとどめるのが消火器の役割ですので下記の点に注意し目にしやすく容易に持ち出せる場所に設置してください。
- 湿気が多い場所や直射日光があたる場所は避ける。
- 雨風などにさらされる屋外では格納箱に入れる。
- ガスコンロやストーブのそばは避ける。
|
 |
 |
 |
 |
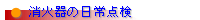 |
 |
 |
 |
 |
消火器の耐用年数は購入した機器によって違いますので必ず確認しておきましょう。
また、一般住宅においては法的な義務はありませんが耐用年数内であっても半年に1度は点検をする事をお勧めします。
点検箇所
- 本体容器やキャップ部分に変形や鋭いギズまたは錆び・腐食がないか。
- ホースに、ひびや詰まりがないか。
- 安全ピンがついているか。
- 圧力ゲージの付いているものは、その圧力値が正常値であるか。
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |

